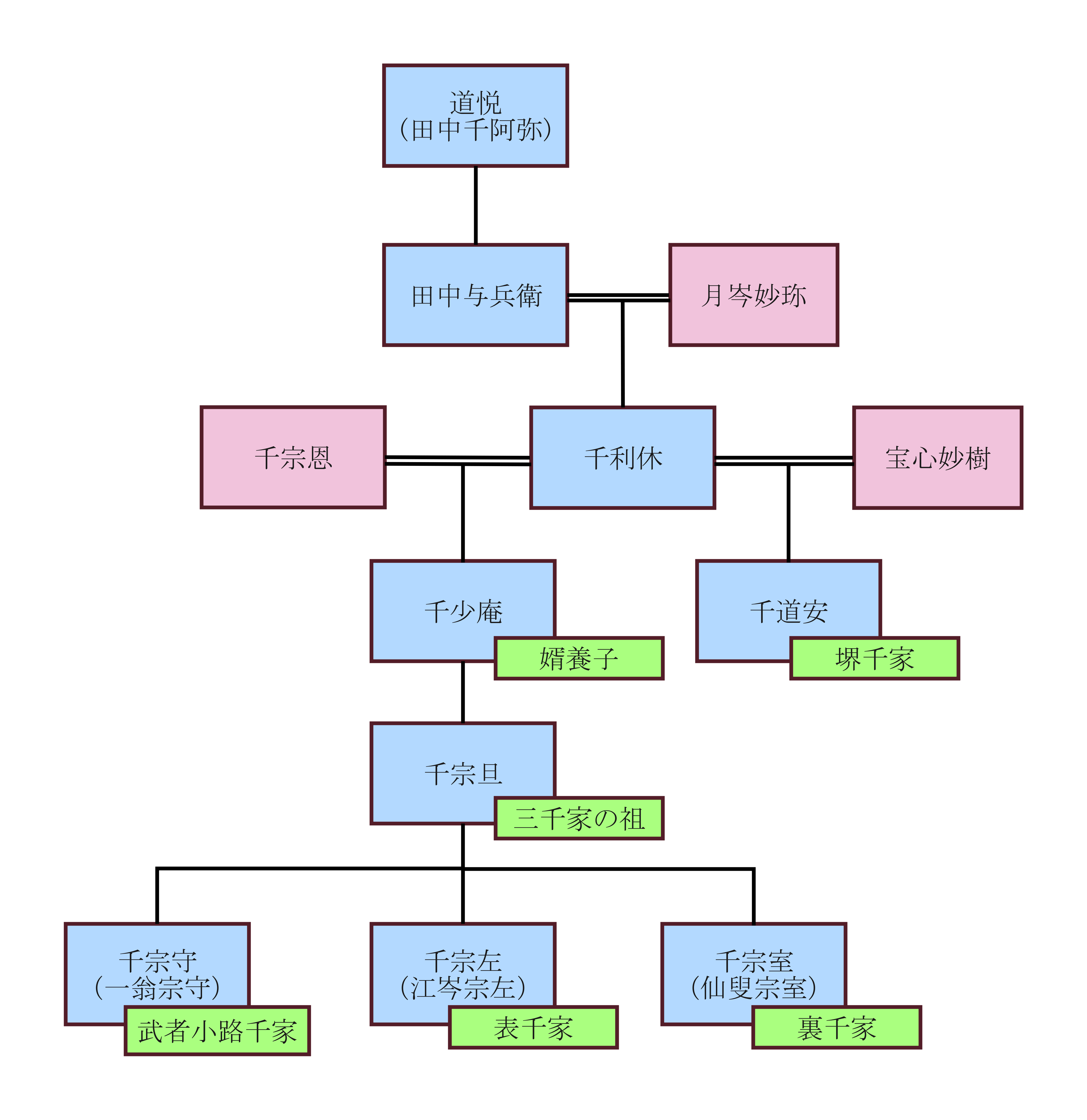千利休(せんのりきゅう、1522年〜1591年)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての茶人であり、茶道を美の境地として完成させた人物として「茶聖」と称されます。
この記事では、利休の血縁・養子・孫を中心とした系譜を整理し、「三千家(表千家・裏千家・武者小路千家)」がどのように成立したかを明らかにします。
1.千利休の家系図
この系譜から、三千家という枠組みが利休から孫・曽孫にかけて血縁を軸に成立していることがわかります。利休の直系として、道安の系は一時「堺千家」を名乗ったものの、後継者がなく断絶し、実際の流派を今日に伝えるのは宗旦由来の三千家です。
参考文献:
2.千利休の家族
祖父:田中千阿彌(たなか せんあみ)
千利休の祖父であり、室町時代の堺の商人。新田里見系田中氏の一族とされ、足利義政の同朋衆の一員でした。応仁の乱の際に堺に逃れ、その後、足利義尚に仕官しました。利休はこの祖父の名を取って「千」の姓を名乗ったと伝えられています。
父:田中与兵衛(たなか よへえ)
利休の父で、堺で魚問屋を営んでいた商人です。法名は一忠了専(いちちゅう りょうせん)で、出自は新田里見田中氏の一族とされていますが、確証はありません。利休は幼名を与四郎(よしろう)と呼ばれました。
母:月岑妙珍
利休は母から茶道の基礎を学び、後に茶道の道を志すようになりました。
妻子
初妻:宝心妙樹
利休の最初の妻で、彼女との間に、長男・千道安(せん どうあん)をもうけました。
再婚相手:宗恩
利休の再婚相手で、千家の宗恩(そうおん)とされています。息子の千少庵(せん しょうあん)は利休の婿養子です。
3.利休の子孫と三千家の成立
長男:千道安(せん どうあん)
千道安は利休の長男で、父の後を継ぐことを期待されましたが、茶道界での立場は限定的でした。彼の後、堺の千家は一時的に断絶しました。
養子:千少庵(せん しょうあん)
千少庵は利休の次男で、父の死後、茶道の家元制度を再興しました。彼は京都で千家を再興し、茶道の基盤を築きました。
孫:千宗旦(せん そうたん)
千少庵の子である千宗旦は、茶道の家元制度を確立し、「表千家」「裏千家」「武者小路千家」の三家を分立させました。これにより、千家は三千家として現在に至るまで続いています。
4.現代における三千家
三千家は、現代でも茶道界の中心を占めており、それぞれ特徴を持ちつつも利休の道統を共有しています。
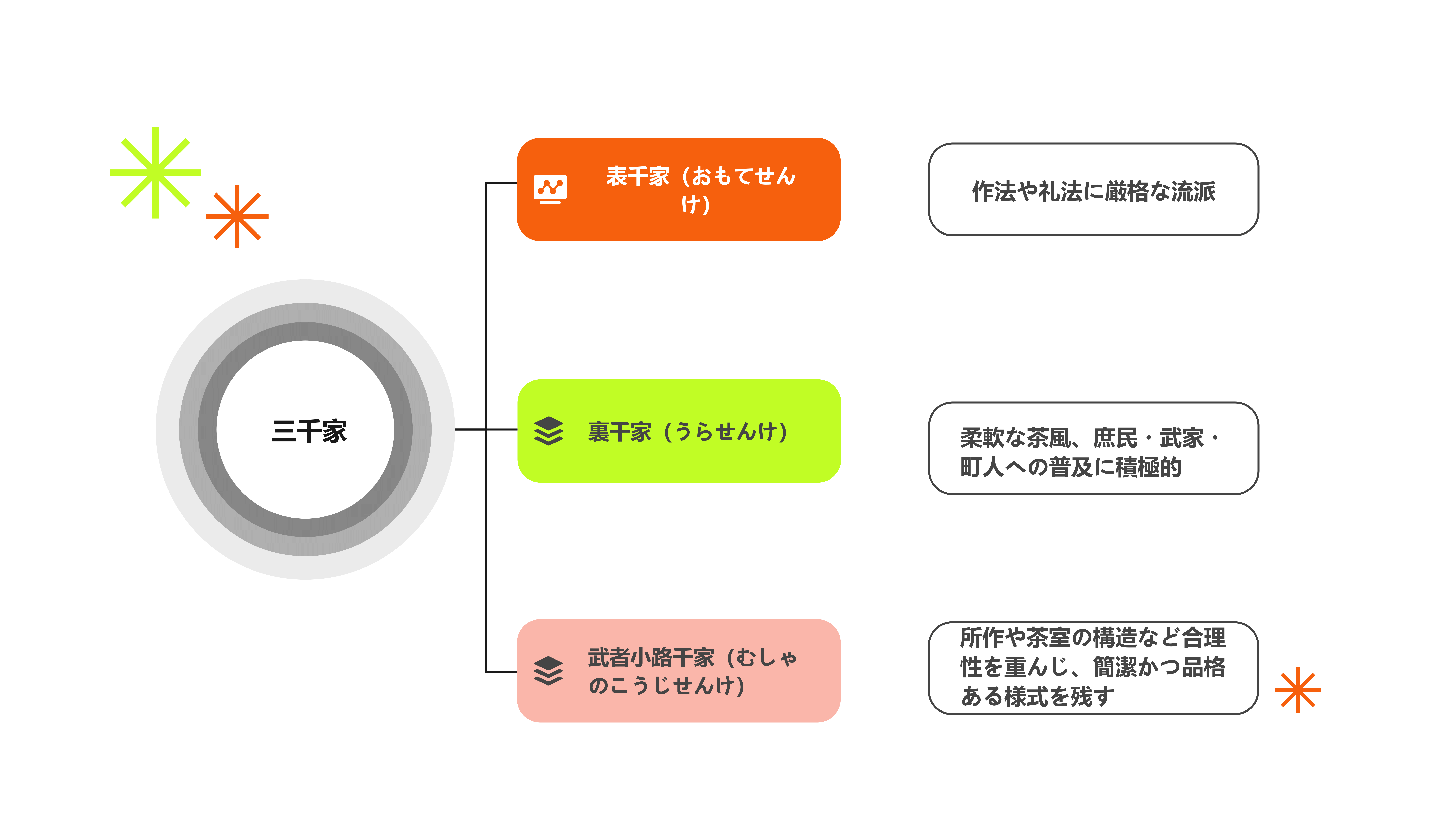
表千家(おもてせんけ) 本家として利休以来の正統を主張。伝統的な所作を重んじ、作法や礼法に厳格な流派。現在の家元は第14代・千宗左(そうさ)。
裏千家(うらせんけ) 柔軟な茶風、庶民・武家・町人への普及に積極的。国際交流も盛ん。「一盌から平和を(Peacefulness through a Bowl of Tea)」などの理念を打ち出す。現・第16代・坐忘斎 宗室(ざぼうさい そうしつ)。
武者小路千家(むしゃのこうじせんけ) 所作や茶室の構造など合理性を重んじ、簡潔かつ品格ある様式を残す。官休庵を拠点として稽古場・茶会などを行い、利休の精神を現代に伝承。
5.家系図作成ソフト
本記事における家系図は、EdrawMaxという家系図作成ツールで作成されました。ドラッグ&ドロップの操作で系図・相関図を直感的に描ける特徴があります。研究報告や発表資料、ウェブサイト掲載用に見やすく整理された系図を短期間で高品質に作成可能。初心者でも編集しやすいです。
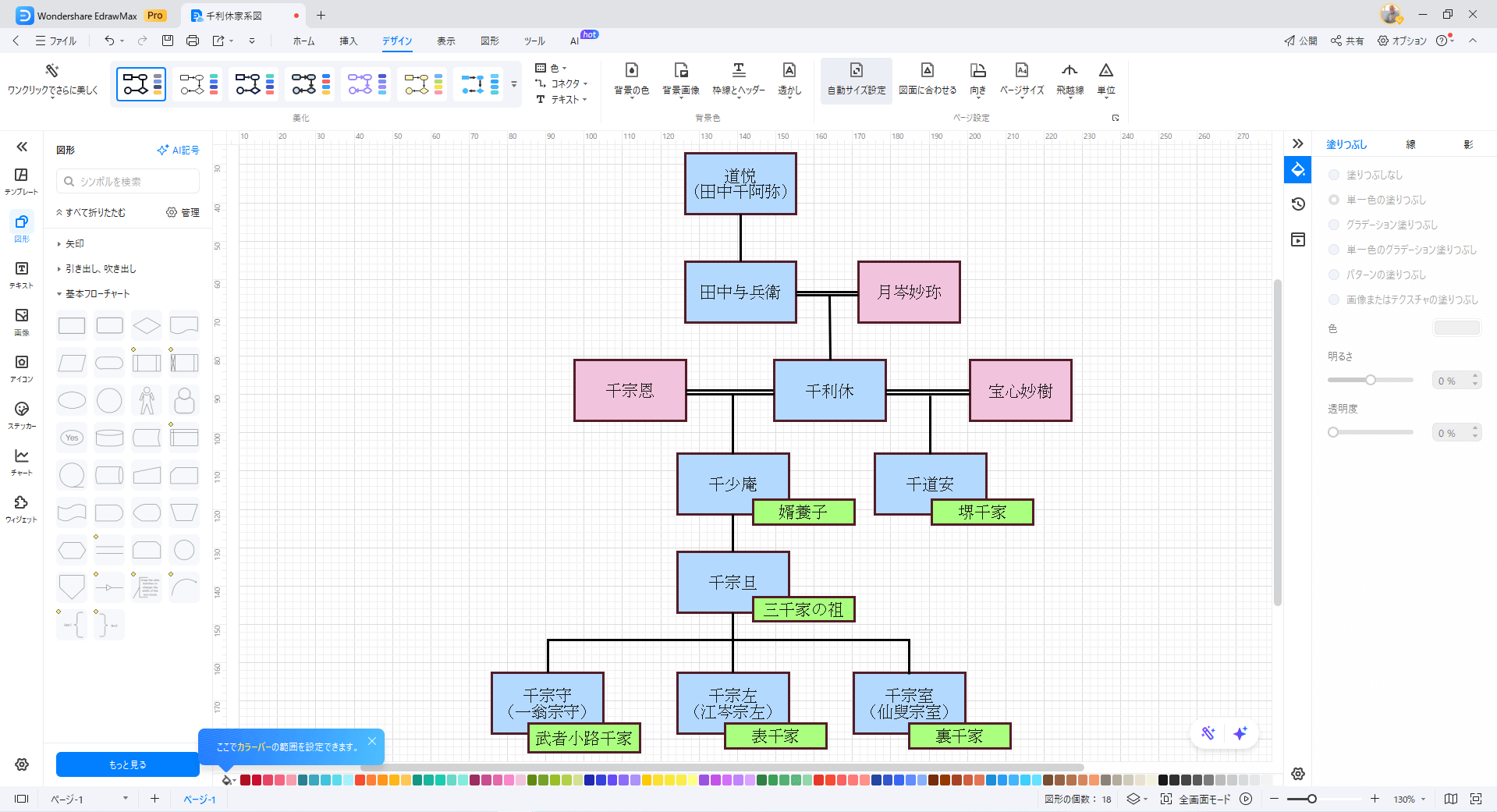
使用した機能:カスタムノード、コネクタ線、人物名の表示、色分け、出力形式は PNGなど。
特徴:
①豊富な家系図テンプレートと素材
ジェノグラム、エコマップなどプロな素材を搭載しています。ドラッグアンドドロップでご活用いただけます。
②高度な編集機能
きれいな色合いを提案するほか、ワンクリックで美しくする機能も搭載します。それらの機能を活用して初心者でもきれいな家系図を作成できます。
③高い交換性
完成品をpng、svg、pdfなど様々な出力形式に対応します。